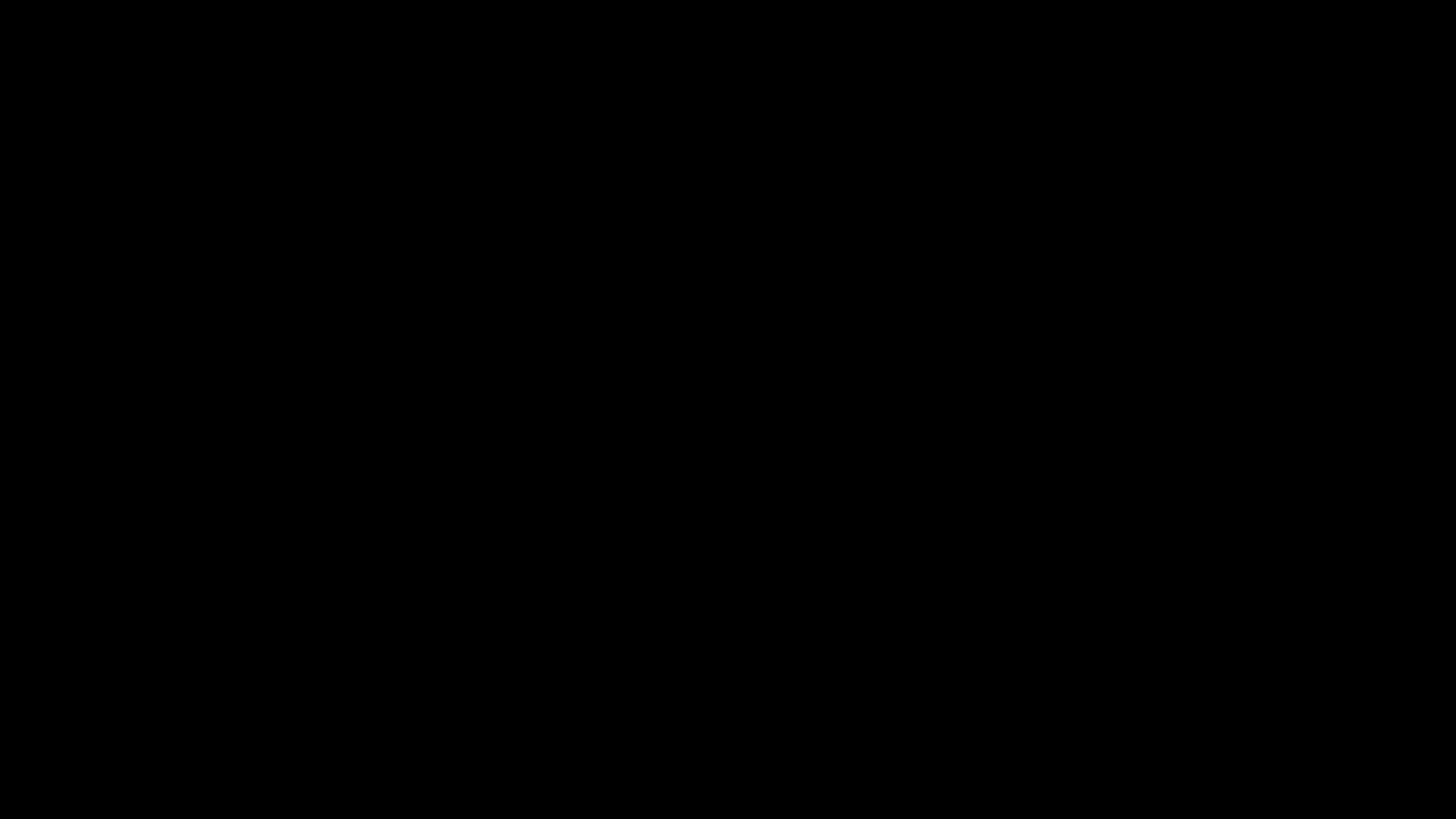この彫像は……

……ヴィクトリア歴代の君主たちよ。
とある幻影が……ここに彷徨い、徘徊している。
その者たちとは故人たちの意志というものではなく……歴史と記憶の影だった。
「アレクサンドリナ殿下」
その者たちの呼応は、はっきりと耳に捉えることができた。
なんとも暖かく、聞き慣れた声だろうか。まるですでに忘れ去られてしまったシージの記憶の奥底からやってきたように。
彼女がまだ幼い頃、時間を忘れてしまうほど夢中に遊んでいる際に、何者かがそうして愛や叱りの念を込めて彼女の名を呼んでいた。
「アレクサンドリナ殿下」。
また彼女がこっそり宮殿を抜け出し、外の情景を見てやろうと思った時も、何者かが促しながら焦って彼女を呼び留めていた。
「アレクサンドリナ殿下」。
そして自分が抱く幻想に憧れ、懸命に木製の小剣を振る時も、何者かが安心したように彼女の名を褒め称えた。
「アレクサンドリナ殿下」。
しかし……
彼女の名をそう呼ぶ者は、一体誰なのだろうか?

アスラン王とドラコ王の彫像は、全員ここに列せられているの。

アレクサンドリナ殿下、こちらの方があなたのお父上、“ガリアを征服された”フレデリック三世よ。傍には陛下の母君、“栄光ある”エリザベス様がおられるわ。
ここへやってきたシージら一行は、みな知らず知らずのうちに歩を緩めた。

……
彼女は探していたのだ。心の内ではいつ探そうとも結果が見つかるわけではないことを理解していようと、彼女の目線は探し続けたい一心だった。
そしてとある石像の前に止まった。
それは未完成の石像だった。今はまだ大まかな輪郭しか見て取れない。
華やかなベールに石像は包まれているも、彫られた痕はくっきりと確認できる。
視線を上に移せば、本来であれば顔であるはずの部位には、僅かに眉と目が確認できるだけで、全体は未だに朦朧としたままだ。
ただ頭上に被られた冠が、ぞんざいながらもこの石像の身分を物語ってくれている。

ここにある石像はすべて、王室お抱えの彫刻家たちが長い年月をかけて彫られたものなの。アーツで彫ることは規定によって禁止されているわ。

ただあなたのお父上、陛下は……あまりにも去るのが唐突過ぎた。

……ああ。

陛下はたくさんのプレッシャーを背負われていたわ。現実にあるものも、倫理におけるものも。

当時この帝国は、戦争による負債とドラコ王室の企てという二つの面に苦しめられていたの。向こうの王室は、これ以上アスラン王による統治は看過できないと考えていたのよ。

でもね、周りがどう陛下を評価しようと、私と私のお父様から見れば、あのお方は……ここにおられるどの王と比べても遜色ない王だったわ。

そうかもな。

だがいいんだ、肝心の私はもう何も憶えてはいない。

あるいはこれが、私の抱えてる父の印象なのだろうな。
「アレクサンドリナ殿下」
今の声はさきの者から発せられたものか?それともここにいる全員からか?
目の前にずらりと並ぶ石像たちは荘厳で、あるいは優しさを見せ、それぞれ異なる面持ちをしている。
シージはいくら記憶の中を探っても、この者たちに関する思い出は見つけ出せそうにない。だが心の内では確かに、不思議とここに鎮座する者たちと繋がってる感覚を覚えてしまう。
ヴィクトリアという姓は、ヴィクトリアの君主、あるいはその序列第一位の王位継承者でしか引き継ぐことはできない。
ゆえにシージはここにいる者たちと同じく、共にヴィクトリアであられるのだ。
しかし彼女は、ここにいる者たちから視線を引っ込めた。
その壮大なヴィクトリアよりも、彼女はノーバート区の小さな酒屋に置かれてる辛口なドラフトビールと、全力で戦闘に挑んだ後に味わう酸味あるポップキャンディのほうが馴染み深い。
そう思って彼女は、くるりと身を翻すことにした。
だが視線を引っ込めたその時、彼女は彫像の後ろに隠れている影に気が付く。

気を付けろ!
シージの声を聞き、一行は自分らが持つ武器を構え出した。

……

どうやら、さっきの痕跡を残していった犯人を見つけたみたいだ。

あれはサルカズの遺体だ。

見たところ百人は超えてる。もしかすればもっとあるかもな……

死体ならほとんど腐って分解されているが、残った装備品や服装を見るに、全員サルカズ王庭の精鋭部隊と、聴罪師の衛兵だろうな。

いや、こいつらからすれば“精鋭”という言葉は侮辱にすら思えるだろう。正直言って、このうちの一人でも襲ってこれば、俺たちは全滅かもな。

じゃあ、彼らと戦った相手って……

……
シージは、傍にいるアラデルの呼吸が重くなるのに気が付く。
死骸の影に、依然とギラつく銀光が目に入った。
まるで歴史という歳月ですら、その光を色褪せることなどできないようだ。
そんなシージは、銀光のもとへと歩み寄る。
帝国の騎士は決して退くことはなかった。
一人、また一人と。
バラバラに斬り刻まれた者がいれば、めった刺しにされた者、火に焼かれた者、あるいは腐食のアーツに蝕まれた者など様々だ。だがどの甲冑にも、干からびてしまった血によってコーティングされている。
五メートルをも超える釘のような投擲物が一本一本、巫術を帯びた状態でこの者たちを串刺しにしている。
しかしこの者たちは未だに陣形を崩すこともなく、戦いに従事している様相だった。
何者であろうとこの者たちを打ち倒すことはできない。王庭の軍だろうと、聴罪師だろうと。
死であっても例外ではない。
そこでシージははっと気づいた。
なぜ……過去四年もの間、ロンディニウムからぱたりと蒸気の噴射音が途絶えてしまったのかと。

蒸気騎士……
(シージがアラデルを支える)
よろめいてしまったアラデルを、友であるシージが支える。

大丈夫か?

……

ちょっとここの空気が良くないだけね、私なら平気。

ただ……カンバーランド家に置かれてたあの蒸気鎧のことを思い出してしまったわ。

この者たちは、対価なんてものに目もくれず、ただただ守ることに徹していた。

それが……蒸気騎士ってものだったのね。

ヴィクトリアの栄光を、その身に背負っているがゆえに。

……いいや。

違うさ。
(剣と剣がぶつかる音や矢の飛び交う音、蒸気が噴出する音が鳴る)
武器同士がぶつかり、弓矢が飛び交う音だ。
これは騎士たちが立ち向かう際に発した蒸気の噴射音だろうか?
こうも溢れんばかりの、まるですべてに立ち向かわんとするこの情緒はなんだ?
シージは目を閉じた。困惑してしまうほどの情緒の数々ではあるが、それでも彼女には分かっていた。

この者たちは……裏切られたのだ。

……裏……切られた?

残された死骸と残骸の配置を見るに、蒸気騎士は攻める側で、ここを守り、そんな騎士たちを阻止していたのがサルカズたちだったのだろう。

バカげた話だと思うだろ?

だがここにあったのは、サルカズに囲まれてしまった蒸気騎士たちが祖国ヴィクトリアを守ったといった英雄的な話ではない。

むしろその逆……これは罠だったんだ。

ここにいる栄誉ある騎士たちは……あらかじめサルカズたちが用意していった包囲網に陥ってしまったのだろう。

……ヴィクトリアの王たちの眠る墓所に設置された、サルカズたちの包囲網に。

……な、ななな、なんたる冒涜だ!

しかし、サルカズ共はどうやってここに入った!?ここを開ける鍵は、王室しか……

ま、まさか……

そうだ、私たちが自らサルカズたちに鍵を渡したんだ。

……キャヴェンディッシュの裏切者め!いや、それともスタンフォード公とかいうあの道化がか!?

どれも違うわ。

四年前に蒸気騎士が消えたということはつまり……全員ここに集められたということよ。

野心に理性を奪われた大公爵程度が、蒸気騎士全員をロンディニウムへ召集することなんてできないわ。

この者たちを裏切ったのは――

ヴィクトリアそのものだ。
燃え盛る宮殿、金色に靡く鬣。
この墓所に入ってから、シージには常にそういった幻影がつき纏ってきた。
怒号する男の声、ヒソヒソと暗い隅で話されている企ての声が聞こえてくる。
ため息、そして呪いの言葉。
狂ったような金切り声と、絶望に満ちた哀号。
叫びも、叱責も、嗚咽も、失笑も。
そして――
ポタリと。
涙が滴り落ちる音も。

シージ……

ここにいる蒸気騎士たちは……
ダグザは極力嗚咽を抑えようとしていた。どんな苦境に立たされようと、いつも騎士と自称するこの少女は一度だって涙を落としたことはないのだから。
だが今、そんな彼女の頬には大粒の涙が流れ落ちていた。

なんで、なんでなんで……どうして……
そんな震える少女に歩み寄り、そっとシージは抱き締める。

すまないダグザ、私の言葉が悪かった。

ヴィクトリアを形作っているのは何も議会と貴族だけではない。私も、貴様もヴィクトリアの一員だ。

だがそれでも、今もこの者たちのために涙を流してくれる者がいてくれた。

とはいえ、今の私たちにはもう無駄にできる時間はない。

貴様は今までずっと、私を王と呼んでくれたな、ダグザ。だからここで貴様に命じる、我が騎士よ。

塔楼騎士ダグザよ、貴様の騎士としての礼を尽くし……

ここにいる者たちに……裏切られたと知りながらも、決して栄光を捨て去ろうとしなかった戦士たちに向けて。

私たちの最上の敬意を払ってやってくれ。

三十、三十一、三十二……

なんて……数なんだ。

……

この者たちは全員、ここで死んでしまったのか。
ダグザは一つ一つの静止してしまった甲冑に、しっかりと視線を向ける。
そしてその一つ一つに、丁寧に弔礼を尽くした。
たとえ甲冑の中にいる者がすでに戦死して何年経とうが、あるいは今の彼女が儀礼用のサーベルではなく奇怪なカギ爪を持っていようが、彼女は儀礼の過程を一つも省くことなく完遂させた。

あんたも騎士だったのか。

かつては、な。

アタシもこの者たちと同じ……本当ならヴィクトリアを守るべき騎士だった。

塔楼騎士として……

ほとんどの人は、その塔楼騎士を一種の貴族の名称として捉えているようじゃないか。

ああ。国王陛下が去ってから、塔楼騎士は誓言に立てたはずの守護する相手を失っちまったからな。

おかしな話だろ。もう誰もいない宮殿を、気取った騎士たちが守っているだなんて。

それでも毎晩毎晩、アタシらは塔に立って見張りにつくんだ。アタシらの背後のある宮殿にはもう誰もいない、目の前にある街からでしか明かりが見えてこないってことを知りながらな。

お嬢ちゃん、聞いた話なんだが、あんたはとある伯爵の娘らしいじゃないか。

でも今あんたからそれを聞くと、塔楼騎士も簡単な仕事じゃないらしいな。

……アタシの母親はマンチェスター伯だ。

とはいえ今の我が一族が所有しているのは、せいぜい辺境の都市にポツンと置かれてる伯爵邸しかないけどな。

母親に愛されてきたんだな。わざわざあんたのために、退路まで敷いてやったんだから。

守るべき王を持たない塔楼騎士は安全な身分だと、あんたの母親はそう思ったんだろう。

王ならいつかは戻ってくる、その時になれば塔楼騎士も雪辱を晴らせるって、アタシの先生が言ってた。

サルカズ共が塔楼騎士の門をこじ開けてきたその時には必ず、ってな。

サルカズは宮殿に手を出さなかった、少なくとも表面上は。向こうも弱みを手放したくはないのだろう。

だが無論向こうからすれば、塔楼騎士は邪魔者でしかないとは思うが。

アタシたちならすでに全力は尽くしたんだ。

塔楼騎士の主力は先の陛下と共に散ってしまった。残されたのは騎士の教師ら数名と……自暴自棄になったヤツらだけだ。

それでも、アタシたちは全力を尽くした!

すでに一度は屈辱を受けてきたんだ、これ以上受け続けるわけにはいかねえだろ!

獅子王が吊るされた頃、あんたはまだ生まれていなかったはずだ。

だから自分で自分に、そんな重い責任を課す必要はない。

だがアタシは、もうすでに塔楼騎士として尽くすと誓いを立てた!王から叙されなくても、アタシはもうすでに騎士になんだよ!

……なのにあいつらはアタシを騙したんだ。最後の攻勢に出るって言いながら、先生たちは最初から企てていやがった……アタシを生かすためにって。

アタシを塔から送り出した時、フィン師匠は重傷を貰っちまったんだ。彼の甲冑からはダラダラと血が止まらなかった。

師匠のあんな顔は、初めて見たよ……これでようやく解放されるって。

屈辱を被りながら生きる人生をようやく終えることができるって、ようやくこの悔やみきれない思いもここで終わるって、言ってた。

……

なんでだよ……なんでアタシに一言も言わずに勝手に逝きやがったんだ師匠!アタシもお前らと一緒に死にたかったのに……!

アタシも一緒に……

そう身勝手に死のうとするもんじゃない。

死ぬのは簡単さ。矢傷でも刀傷でも、傷口からの感染でも、ほんの少し活性化した源石を貰えば簡単に死ねる。

だが、生きるのはすごく困難なんだ。生きるってことはな……“死ねば楽になれる”という思いと常にぶち当たることを意味する。

あんたはもう立派なもんだよ。素敵な仲間と出会って、自分を信じてくれた人たちの期待に応えながら、ここまでやってきたんだから。
年上の傭兵が軽くダグザの肩を叩く。
相手はつい知ったばかりの人だというのに、ダグザは彼から死んでいった仲間の手の温もりを思い出した。彼らも昔は、こうして優しく彼女の頭や肩に手を置いてくれていた。
ロンディニウムを出てから、ダグザはきちんと彼らを偲んではいなかった。
なぜなら戦いはまだ終わっていない、終わるまで故人を偲んではならないと考えているからだ。
だが蒸気騎士らの欠損した甲冑を目にした時、塔楼騎士たち最後の戦いの情景が彼女の脳裏から浮かび上がってきた。
彼女は理解できなかった。こんなにもこの地を愛してる者たちがいるのに、なぜこんな結末を迎えなければいけなかったのか?
なぜ英雄はひっそりと死ねばならず、勝利を迎えてやれなかったのか?
そんな節々の思いが込み上がった彼女は、とうとう我慢できなくなった。

いいんだ、俺の後ろに隠れてるといいよ。今は少しだけ、泣くといいさ。

うっ……あぁ……
ダグザらの周りには、甲冑が静かに横たわっていた。

……

アラデル、緊張してるみたいだが。

……そう?

あなたは一体、この蒸気騎士たちをどう見ていたのかなって、考えていたの。

二十六年前のあの事件を阻止できなかった彼らのことを。

分からんな、あまり気にしたことはない。

だが昔……ガウェインってヤツから聞いたことがあるんだ。当時、蒸気騎士たちはロンディニウムにいなかったようじゃないか。

議会が彼らを移したのよ。

まあ彼らが戻ってきたところで、どうせ何もできなかったはずだけど。

そういう貴様はどう思っているのだ、アラデル?

貴様は蒸気騎士をとても崇敬していたのだろ、見て分かる。

崇敬……には遠く及ばないかもしれないわね。

もしまだ陛下がご存命でいたら、最後に叙される蒸気騎士はサー・チャールズ・リッチだったはずよ。

だってそれから二十数年経っても、一人も蒸気騎士は生まれてこなかったんだから。

これって、ある種の警告なのかしら?誰も知る由もない、抗いの代償とか?公爵らが各々、刃を互いに突き立てる兆しだったのかしら?

もしかすれば……裏切りはその時からすでに始まっていたのかもしれないわね。

一体どれだけ緩やかな死だったのか……私には想像もつかないわ。

ヴィクトリアは、ヴィクトリア自身によって殺された。
あの声が、不満そうに呻く。
だがシージはそんな声に耳を貸さず、落ち着きながらも力強く、先ほどの言葉を繰り返した。

貪婪と、野心と欲望によって繋ぎ合わされたヴィクトリアが、ヴィクトリア自身を殺したのだ。

じゃあアレクサンドリナ殿下、あなたはこの国を建て直そうとお考えなのかしら?

……
声が静まる。声の主たちも彼女の答えを待っているのだ。

私なら、私の為すべきことを為すだけだ。