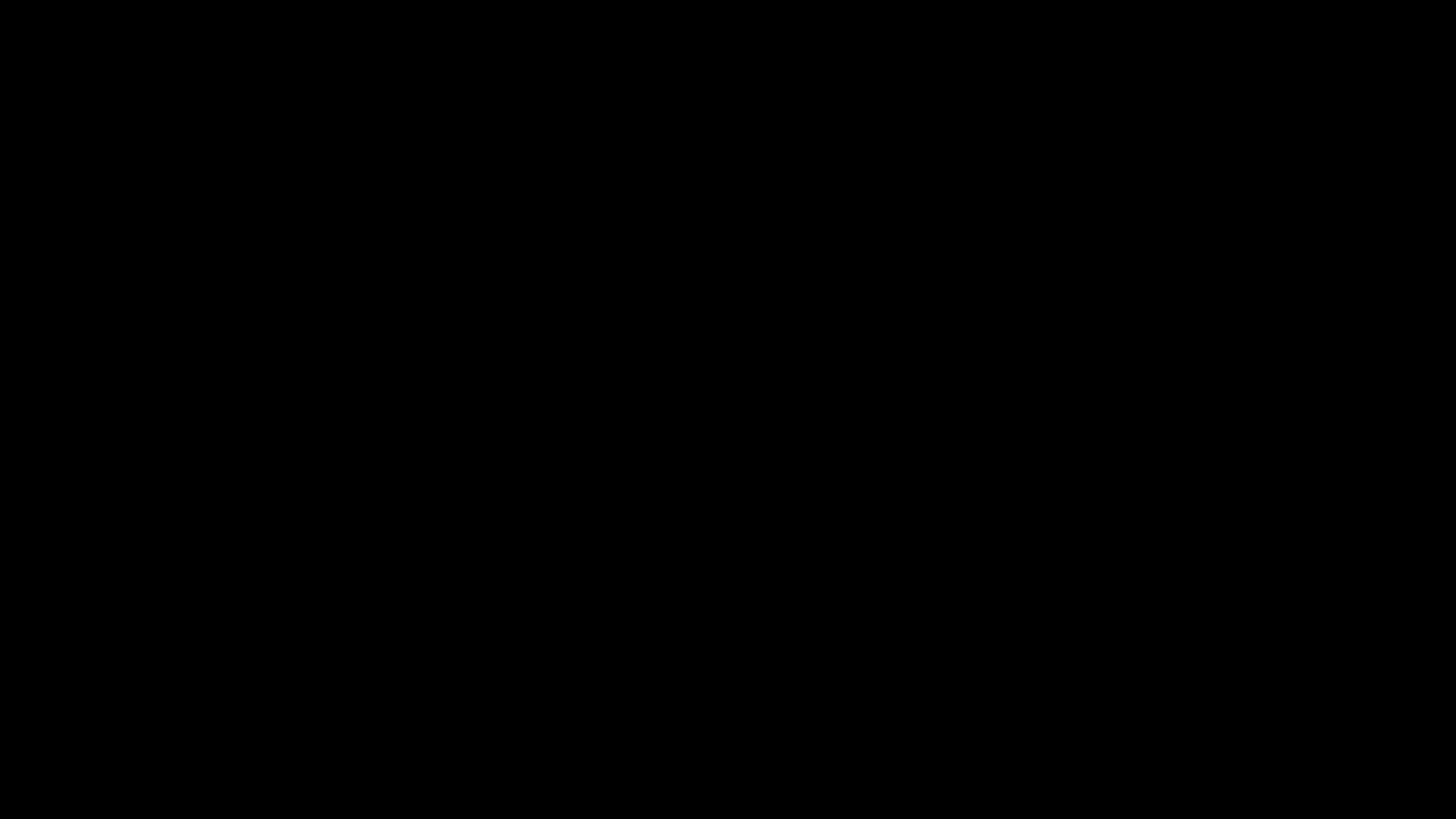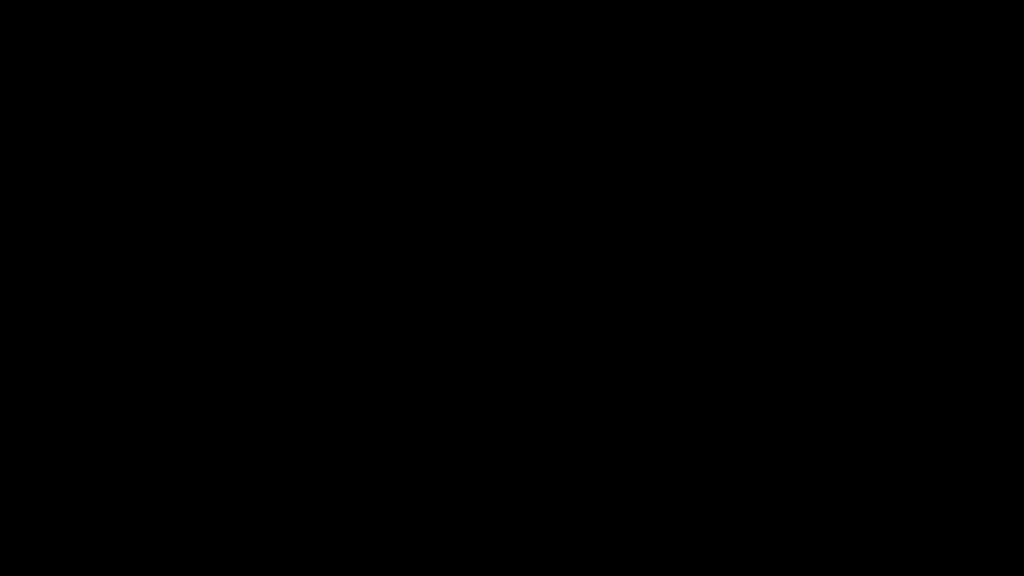“私の心を詩に織り交ぜよう。”
“ああ、来たる混沌の時代に生きる君よ。”
“それを追う私の魂もいずれ知ることになるだろう。”

やっぱりな、連中がこんな天災にぶち壊された石がそこら中に転がってるところまで追ってくるはずがねえぜ。

朝に起こった濃い霧にも感謝しなくちゃな、そうでなきゃここまで逃げられなかったはずだぜ。

あっ、気を付けて。防護装備を持っていないんだから、ここでケガでもしたら感染してしまうかもしれないよ。

モニ、キミもだ。源石が群生してる環境は、感染者にとってもっと危険な場所だからね。

ありがとう、気を付けるね。

……ケリーは寝てしまったのか?

ええ、おそらくはね、気絶じゃないと思うわ、呼吸も穏やかだし。寝たら少しは痛みも和らぐはずよ。

……それでもはやくケリーに応急処置をしてあげないと、手遅れになるかもしれないわ。それがどうしても心配で。

そうだね、急ごう。

……みんな、ガッカリさせちゃったかな?

まさか。あなたも言ってたじゃない?私たちがこうして止むを得ずダブリンと戦うハメになっているのは、向こうが二人目の“リーダー”を必要としていないからだって。

向こうにはまだ私たちなんかよりも大きな目標を掲げているんだから、このままずっと私たちを追い掛け回すなんてこともないはずよ。

こんな逃げ回る暮らしも、私たちみんなとっくに慣れたわ。だから心配しないで、我慢ならできるから。

でも、この先はどうするのかしら?まだあなたの考えを聞いていないわ。

……

私もまだ決まっていないんだ、ごめんなさい。

そうだ、廃墟の奥だったら源石結晶もあまり生えていないのかもしれない。そこでしばらく隠れられる場所がないか、少し見てくるよ。

みんなも、そろそろ休んでおかなくちゃならないしね。

でもあっちって、なんだか人がいなかった?

見たところ一般人のようだけれど、やっぱり避けたほうがいいと思うわ。前にも言ってくれたでしょ、こんな場所にいる人はほとんど怪しい人だから、気を付けなきゃいけないって……

……

……いや、大丈夫だ。

……リードちゃん、もしかして怖がってる?どうかしたの?

(まさか……あの人がここに来た?この近くに?)

なあ、あっちの人、なんか歩き方が変じゃね?

見ないほうがいい。

ヒィ――あ、あの人なんで――
(リードがアーツを放つ)

彼女はもうすでに、この世を去ってしばらくは経っているはずだ。

アーツによって身体が操られているんだよ。私たちはこの前見た、あのダブリンの兵士たちと同じように。

どうして、一般人なんかを?

分からない。

――さあ、ついて来て。アーツに操られたこの者たちは、私が対処するから。

ここは暗くて見え辛いから、階段を降りる際は源石結晶に気を付けて……モニ、ケリーをおんぶしてもらってるけど大丈夫?

大丈夫。あなたの火があれば、ものは見えるから。

分かった。なるべく深いところまで行こう、でもあまり大声は出さないようにね。

――

ここは……
……ゲール王の王宮?
すでに滅びて久しい王朝に対して、その灰石の遺骸には不退転を貫いた戦士たちの甲冑が敷き詰められていると考える者がいれば、黄金の冠は今も深い森の奥に隠されていると考える者もいる。
現代ロンディニウムの城壁をもって王宮の恢弘さを引き立たせようとする者、果てなきクラスド内海で英雄ひしめく時代の美徳を讃える者、そしてヴィクトリアの陰影によって我々の時代は徐々に蝕まれていったことにに嘆く者。
この古城はターラーの悲哀のモニュメントであると、怨恨の亡霊であると、人々はそう考えていることだろう。
しかしこの王宮はただ静かに丘の上に佇んでいるだけで、王宮が建てられるよりも前に存在したこの地の心臓をあらわにしていただけだった。
野草は生え散らかし、蔓に絡まれるがままだった。

ここって、めちゃくちゃ昔のものなんじゃねえのか?五百年前?いやもしかしたら一千年前とか?

シーッ……ケリーちゃんが起きちゃう。

あっ、わりっ……ちょっと驚いちまっただけなんだ。いや、ちょっとじゃねえな。

俺たちって、毎年ゲール王物語の演目を演じてきただろ?だから俺たちがターラー王国の臣民の子孫で、それでターラー人って呼ばれてることなら分かってるんだけどさ……

……それがまさかすべて本当だったなんてね、昔じゃ信じられなかったわ。

それにターラーの戦士たちの武器を融かし、それで王朝の運命が翻ったっていう伝説の熔炉も……

……かなり前にね、あちこちで吟遊詩人を探し回ってる人と出会ったことがあったの。

伝説の多くは後に生まれた者たちによって作られたものだけれど、その物語の中には、今も史実の痕跡が残されていることだってあるんだって、彼が教えてくれたわ。

だからリードちゃん、あなたはこういうのたくさん知ってるんじゃないのかしら?

……

どうしたのリードちゃん?もしかして、あまりここは好きじゃなかった?ここに入ってから、あなたずっと黙りっぱなしよ?

……そうかもね。

小さい頃、よくターラーの伝承の物語を読んでいたんだ。いつの間にか寝てしまっていたぐらいにね。

ヴィクトリア王室の者が書いたものにしろ、ターラーの文化を残そうとする者が書いたものにしろ、彼らはいつも“ドラコの天性は闘争である”と本に綴られていたんだ。
最初にゲール族を率いたドラコが、川を干からびせながら南下していき、王座を相争っていた骨肉たちからも逃れ、ターラーの地を切り拓いた伝説。
ヴィクトリアの赤き龍がターラー最後の遊牧をしていたドラコの首領を殺し、片言も話せないほどのその赤子にゲール王の称号を賜った伝説。
それからターラーのドラコは王宮に囚われ、“放逐王”が自ら冠を脱ぎ捨てて荒野を二十年も彷徨った後に帰還した際、最後には王座に就いていたその肉親に殺された伝説も。

ターラーの歴史は、こういった物語でありふれている。ドラコの王宮には、陰謀と骨肉同士の血が染みわたっているんだ。

だから……私はここが怖い、いくらああいった憧れや幻想があったとしても。
いつか姉さんと殺し合わなければならないのではないかと、それが何よりも怖いんだ。

……それよりも、天災が残していった源石の結晶、ここならあまり見かけない。

安全なはずだから、ひとまずここで休もう。

そりゃいい。ほらモニ、ケリーちゃんを降ろしてあげよう、手伝うよ。

ここに寝かせてあげましょう、ちょうど風がない場所だから。

ここの壁は頑丈だし、居場所も分かりづらいわね。夜に火を起こしても、たぶん外からは気付かれないんじゃないかしら。

なあおい、リードが――

まあまあ、行かせてあげましょ。
“ターラーの地を再び赤く染め上げないために、ドラコの同族が再び互いに刃を向け合わなくていいように、私はここで戦士としての誇りを棄てよう。”
“赤き龍の炎が、熔炉の中から黄泉の戦士らを蘇らせるその日まで。”

……
リードはふと、微かな音を耳にした。
そして目の前にある錆びついたモノに触れようと伸ばしていた手を引っ込めたのである。

まだ……生きてるの、これ?

誰にだって動かすことができるものだからね……誰かが再びこの物体に火を点けたんだ、おかしいと思うところなんてないでしょ?

……そうか、あの人が来ていたんだね、どうりで。
隙間から、彼女は紫の炎を目で捉えた。

ここは王宮だった場所だから、あの人が来てもおかしくはない……きっと嘲笑っていたでしょ?伝説の王が、こんなものしか残してくれなかったなんて。

ここにはあの人の炎が燃えている、だから近くには眠れない死者たちが彷徨っているんだ。

なんの謂れもなく死の炎に呼び覚まされた、死を望む放浪者たちが。

やめて……近づかないで。

そういうキミだって、あの炎が怖いんでしょ?

……

私には分かる、キミはあの炎を消したいんだね。

……うん、あれは苦しみしかもたらしてはくれないから。

そんなことをするのであれば、キミをここから通すわけにはいかない。

あの人はダブリンに火を点けてくれたんだ。自分ではそれと同じ炎を点けることができない、それをキミ自身はよく知っているでしょ?

確かにあの人は悪いことをしてきた、たくさんの綺麗事を話した。でも、仕方がなかったんだ。貴賤も、聖人も暴徒も問わず、彼女は多くのターラー人を従えたでしょ?

キミにそんなことができるはずもない。

いいや……私にだってできる。

そういった犠牲は不可欠だったなんて、私はそうは思わない。あの人の方法でしかターラー人たちは救われないなんてことも、なおさら。

しかしとうの昔から、あのオーク郡で起こった大火事から、あの人はみんなを率いてきたんだよ。
リードはあの時街中で倒れ込んでいた、満身創痍の女の子のことを思い出す。彼女はその子に手を差し伸べ、「逃げよう」と声をかけようとしていたが、手を伸ばしてしまえば、その子もまた灰にしてしまうのではないかと恐れていた。
だから彼女のもとへ近づいていったのは、姉のほうであった。
そして彼女にこう訊ねた、“生きたいか”と。
すぐ傍には下水道がある。そこに潜れば、これ以上あの憎たらしい貴族たちから追い掛け回されることもなくなる。
彼女はマンドラゴラ。そこから逃れ、最後にまたそこへ戻っていったマンドラゴラだった。

結局キミは、誰にも手を差し伸べられなかった。

……

うん。もしあの時私が彼女に手を差し伸べていたら、また色々と違っていたのかもしれない。

もし本当に救われたのなら、彼女はあの日放火した者たちと同じように、悪事のための力を得るのではなく……ほかにも色んな道を行くことができたはずだ。

けご実際、他人に操られるのを許してしまうほど、キミは自分の力を恐れている。

……だからキミの姉さんはキミに失望しているんだよ、ましてやほかの人だなんて。

……いや、それは違う。キミが言ってるのはすべて昔のことだ。

今の私は、きちんとみんなの手を握ることができたのだから。

私が彼らの手を引いている、なんてことは言えないけど、でも彼らが前に進もうとするのであれば、私の炎で道を照らそう。たとえ私が彼らに引っ張ってもらうことになったとしても。

あの人がもし……もし今の私を見れば、きっと失望なんかはしないはずだ。

キミがその仲間を得たのはたまたまだ。

彼らの前で、キミはあたかも戦えるようなフリをし、綺麗事を並べて人々を呼び寄せている……自分がいかに力を有しているのかを見せつけているんだ。

所詮キミは、あの人の真似事をしているだけだよ。

所詮キミは、あの人の影だ。あの人はどんなことも完璧にこなしてくれるが、それに比べてキミはあまりにも優柔不断で、優しすぎる。
ターラー人の居住区に火を放った、あの軍人たちのことを彼女は思い出した。彼らはターラー人たちがいかに独善的であるか、オーク郡の法令に不公平と抗った、文字すら読めないターラー人たちを嘲笑っていた。
姉さんが最後に先生へ言った、いずれ起こるであろう出来事がこれだったのだと、彼女は分かっていた。
ヴィクトリア人が自ら、この憎しみ渦巻く炎を燃やしたのだ。すべてを焼き尽くすまで、この炎が消えることはない。
目を閉じるなと、姉さんが私に言う。我々の日常が次々に、如何にして壊されていくのかをその目に焼き付けるのだと。
そう言って焼き焦げた黒い死体たちが転がる中、死の炎を操るドラコは手を掲げてアーツを放った。
紫色の冷たい炎が、死者たちを焼き焦がしている烈火を覆っていく。
実際のところ、その死の炎はほとんど命を奪ったことがなかったのだ。姉さんはただ、死んでも故郷を燃やした者たちに復讐することをできるように、死者たちに再び立ち上がる許しを与えていただけだったのだ。

……そうだとしても、私は後悔していない。

今までずっと、あの人のやってることは正しいと思っていた。

「ターラー人たちの理想郷のためなら、我らは命すらも燃料とし、火にくべよう」と……

あの人の傍にいた時、私はずっとそうやって自分に言い聞かせていた。

……けどその命が燃え尽きた後、あの人の国には一体誰が残っているっていうの?

確かに私は迷ったよ、何度も振り向いたし、逃げもした……

でも私は後悔していない。

ここまで逃げてきたからこそ、私はあの人とは違う景色を見ることができた。あの人とは違う言葉を見つけることができた。

だから、あの人のことを思い出して、怯えるようなことならもう起こらないよ。

私はもう絶対に……自分の影に囚われることはないのだから!

この王宮を見た時、キミは恐れていたじゃないか?

自分や自分の“仲間”たちがどこへ向かうのか、その答えすらもキミは出せていない。でも、心の底では最初から分かっていたはずだ。

私にならない限り、お前はダブリンの夢の中で、自分の居場所を見つけ出すことはできないぞ。

――だからラフシニー、お前は一体どうしたいのだ?
あの大火事から自分たち姉妹へ向かってくる死者たちのことを、リードは思い出した。

……止まって……
その者たちは、顔の見分けもつかないほど身体はズタズタに崩れかけていたが、目だけは渇望の炎を宿していた。
ヴィクトリア軍人への復讐を遂げ、自分たちのために火を点けてくれた人のもとへ近寄ろうとしていたのだ。

もう、止まって……

もう……眠って!
(炎が紫から赤へと変わる)
――気付いた時、彼女の一番近くにいた者はすでに彼女の目の前で倒れ込んでいたものの、空洞となったその目は依然と彼女を見つめていた。
一瞬にして過った明るい火の光を浴びて、彼らの中に燃える死の炎が消え去ったのだ。

……ごめんなさい、姉さん。ごめんなさい……

私、わざと姉さんのアーツをかき消したわけじゃ……

――よくやった、ラフシニー。
恐怖に震える中、彼女は顔を上げる。
姉が初めて、自分に称賛の微笑みを向けてくれたのだ。

よくやった、よくやったぞ、ラフシニー。お前の炎は、とても輝かしいものだった。

いつも悩んでいたのだ。どうすればほかの者たちにお前を認めさせてやればいいのだろうかと、どうすればお前は自分の力を示すようになるのかと。

さあ、もう一度お前の力を見せてくれ。私の炎を消し去ることができるかもしれないお前の炎を、この私に見せておくれ。

私を消し去る、その炎を私にも見せておくれ、私の愛しい妹よ。