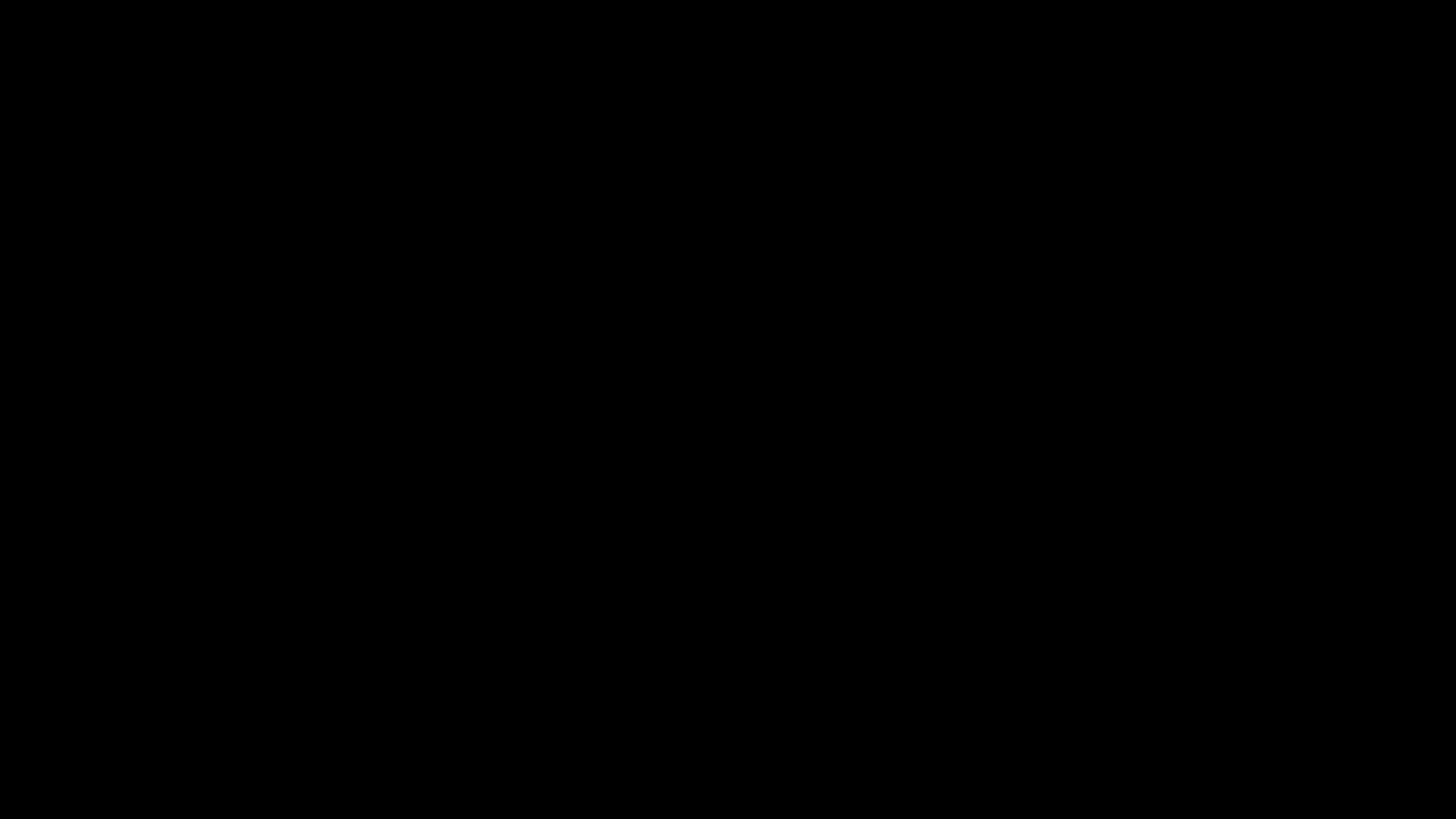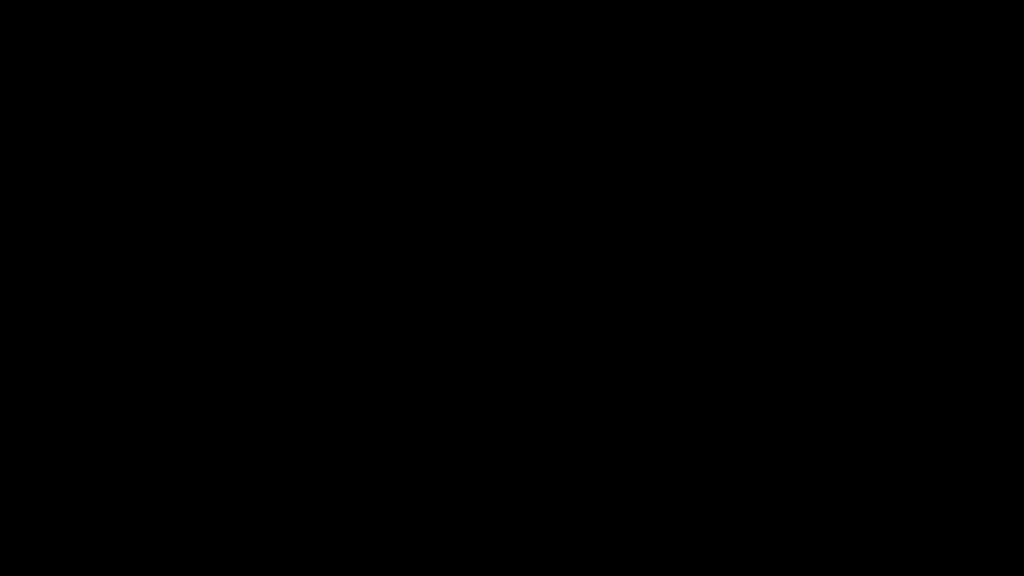私の炎が怖いのか?だが、お前の炎とて私のと一緒だぞ、ラフシニー。
この炎は永遠に燃え続ける炎だ。炎の明かりを遮る、あるいは炎そのものを揉み消そうとするも、すべてはただの徒労に過ぎない。
人に見られることも恐れる必要はないぞ。なぜ恐れられてはならないのだ?
私の中に、火が燃えていることは昔から知っている。触れば痛みを感じるが、時間が経つにつれ、痛みは私が感じるよりも前に現れるようになってしまった。
両親が戒めてくるには、その生まれつきの火は呑み込み、隠し、誰にも見つからないようにしなければならないらしい。
しかし私は、姉がいつもこっそりと自分の嫌ったものを燃やし、それでもっと自分の望みに合うモノを手に入れていることを知っていた。
私も、そういうことはできるのだろうか?

お父さん、本屋に連れて行ってもらえないかな?
ある日の朝、私は姉に扮し、姉の口調で両親に話しかけてみた。
姉が毎度要求してくる際の両親はいつも、まるで火に焼かれるのを恐れてか、怯えながらも愛おしそうにその要求に応えてくれる。
私は姉と同じ顔と声を持ち、着こなしも同じだ。私が姉に扮することはできないはずがない。

……明日にしよう、ラフシニー。父さんも母さんも、今日は疲れちゃったんだ。

お父さん……私だって分かるの?

当然じゃないか、娘二人の見分けがつかないわけないだろ?
それからあの雪が降る夜に、私はようやく分かった。両親が応えてくれなかったのは、私の要求があまりにも小さいものに過ぎなかったからだ。
もし姉だったら、新しく刷られたばかりの本すらも要求していたのではないだろうか。
その日、私ははぐれないように、必死に姉の後ろを追いかけていた。
団欒を告げる鐘の音はすっかり鳴りを潜めてしまったが、私たちにはもう帰れる家はない。

姉さん……私たち、これからどこに行くの?

……お前はどこに行きたいんだ?

わ、分からない……

私たちはもう家を失った。となれば、目に入った家々を適当に尋ねてみるとしよう。

お前はただ、ドアを開けに来た者にこう告げればいい。この雪の降る祝いの日の夜に、私たちは帰る家を失ったんだと。

どれだけ冷たい人であっても、雪の夜に震える子供二人を見れば同情心が芽生えてくるはずだからな。

さあお行き、ラフシニー、怖がることはない。私がずっと後ろで見守っているから。
(ラフシニーがドアをノックする)
冷たい紫の炎に照らされる中、私は震えながら一軒目のドアをノックした。
この炎は、つい先ほど私たちの仇の命を奪い取った炎だ。しかしなぜだか、私が何か過ちを犯せば、その炎は振り向きざま私の命までをも奪ってくるのではないかと思えてしまった。

――先生は一体、何を間違えたの?
ターラー人が住まう街では、よく演劇が催されると聞く。それとその日は大雪が降っていたため、先生は何時まで経っても帰っては来なかった。
姉さんが私を呼んで、先生の書斎に座らせる。私の質問には答えず、ただ暖かな目を私に向けてくれていた。
姉さんは私にとても失望していた、私には分かる。こんなこと、聞くまでもなく自分でも分かっていたというのに。

……先生は私たちに、無辜なる者たちの暮らしを破壊し、ターラー人とヴィクトリア人との間にある確執を煽り立てる方法を教えた。

しかも……あの時ヴィクトリア人が私たちの父さんと母さんを殺したように、先生も落ちぶれた政敵を陥れて殺害した。

だから、先生の命を奪うのは……何も間違ってはない。
姉さんはいつも正しいことをしてくれるけど、私にはできない。
姉さんから貰った槍を、いつもあの火が燃えている槍を握りしめようとするも、私はどうしようもなく手が震えてしまう。
この時だってそうだった。

私……間違って、ないよね?

いいや違うぞ、ラフシニー。

先生にとってみれば、死すらも自らの理想の導き手に過ぎないのさ。

彼は今まで、私たちに陰謀と権謀術数を教え込み、私たちの自由と尊厳を引き剥がしていった。それが憎いと思うのも当然だろう、だがそれも所詮は憎いと思うだけだ。

先生が憎いと、嘆かわしいと思える所以は、先生がそういった手段を熟達していたところにあるのではなく、抱えている野心があまりにも矮小だったところにある。

先生が望んでいたのも、所詮容易く砕け散ってしまうような空想にしか存在しない国家と、彼に代わって冠を戴く、我々という傀儡だけだ。

私が今から手中に納めんとする権力は、先生のあの狂乱じみた空想などよりもよっぽど大きいものだよ。

――それで、お前はどうしたんだ、ラフシニー?お前は一体何を望んでいるのだ?

お前の身体に流れる血と教養はお前を高尚なる存在に仕立て上げてくれる、いいことだ。だが何も望むものがないとなれば、私もお前にどんなものを残してやればいいのか分からない。

さあ、言ってごらん?今日は大雪が吹雪く夜だ……どれだけ大きな願望も野望も、私が許してあげよう。

……

……
私は答えられなかった。
なぜなら私はただ、暖炉の中で優しく燃える火のような、小さな願いしかなかったから。
だから私は答えることはできなかった。

まあいい、私の可愛い妹よ。自分の願望がどこにあるのか分からないのであれば、まずは私になってみるといいさ。

今後、お前も私も同じ“リーダー”という存在になるのだ。
あの炎に照らされる中、そうして私は姉さんの影になった。

ハァ、ハァ……お前、ずっとアタシの後をついていたのか?いつからだ?

いや、私はただヴィーンから聞いただけ。キミがダブリンの死者の部隊で兄を見つけたって……

キミならきっとここに来ると思っていたから。

お前とはなんの関係もないと思うんだが。

私はずっと……彼らアーツによって操られた死者たちを探してきたんだ、彼らに安らぎを与えてあげたいから。

私なら、この者たちを眠らせてあげられるよ。さっきキミが見たようにね。

……
兵士らが行軍する足音はなくなり、荒野は静寂を取り戻した。
彼女らもまた、これ以上何も話さなかったのである。そしてしばらくして、セルモンは膝を曲げ、仮面に付着した土埃を払い、慎重にそれを兵士の顔に被せてやった。

……ヴィーンの野郎、余計なことを言いやがって。ならあいつ、アタシが初めてダブリンに会った時のことも話したんじゃねえのか?

あの頃はまだ街に住んでいてな。機嫌がいい時は兄ちゃんと一緒にウエイトレスとかの仕事がないか探したり、悪い時はパチンコでヴィクトリア人の家の窓を割って回るような生活をしてたんだ。

ハッ、まああの貴族連中がヴィクトリア人だったかは知らねえけど、少なくともアタシらを農地から追いやった貴族がヴィクトリア人だったのは確かだ。

んである日、路地裏で倒れ込んでるケガをした女を見かけたんだが、あいつはターラー語でアタシを呼び止めて、代わりに手紙を送ってくれって頼まれたんだよ。

あの女がどういう人だったかはなんとなく察した。だからとりあえず手紙を送って、それから女に隠れ家を探してやったよ。

そこでアタシは女に、アタシが思うこの街一番のクソ野郎は、あの法令を出したチョビ髭のヴィクトリア人貴族だって言ってやったんだ。

それから街に屯ってる軍の連中のことも。少し睨みつけただけで人をしょっ引くし、なんなら直接何人も嬲り殺した場面を見たことがあったから、あいつらもぶっ殺さなきゃならねえって言ったんだ。

もし襲う連中が見つからないで亡霊たちが困っていたら、真っ先にそいつらを襲ってやりゃいいって。

でもその女は違うって、ダブリンの目的はターラー人のためにヴィクトリア人へ復讐をすることじゃないって言ったんだ。

それを聞いて兄ちゃんが一番デカい屋敷を持って、一番ド派手なパーディを開いて、自前の貯蓄だけで一区画の農民と武装した部隊を養えるような貴族を知らねえのかって反論したんだ。

んであの女、それはもっと違う、ダブリンはヴィクトリア人からモノを奪ってターラー人を救おうとしているわけではないとかほざきやがったんだ。

その人たちを殺して、元々そいつらが座っていた席に自分たちが座っても、ターラー人の境遇がよくなることはない、むしろ自分らがそいつらに成り代わってしまうって言ったんだ。

ヴィクトリアの礼儀作法を学んで、ヴィクトリア訛りを真似して、ヴィクトリアの貴族に成り上がったターラー人みたいに、ってな……

……その人、ダブリンの本当の目的は教えてくれた?

いや、ねえな。でも後から兄ちゃんがそれを悟ったみたいなんだ。だからアタシらはダブリンに加わるために、そいつらが残していった手掛かりを頼りに探しに出たんだよ。

で、アタシらが移動都市を離れて、近くにあった集落に行った時。

そこに向かう道を歩いてた時にな、アタシ突然、ダブリンがどうやって目撃者たちを消していたのかを思い出したんだよ。

それでアタシは怖くなっちまったんだ、逃げ出したくなるぐらいに。

アタシだって別に、ヴィクトリア人全員を憎んでいるわけじゃねえ。憎んでねえ人たちに、わざわざ噛みつくつもりなんてねえよ。

でも……そうする他なかった。

私、こんなことは言いたくないけど、でも……ダブリンも所詮はただの軍隊みたいなものだ。軍隊であるのなら、向かった先は戦争しかないよ。

分かってるよ、そんぐらいのこと。

冷静に考えりゃ、兄ちゃんたちは間違っちゃいなかった。

間違ってるのはアタシのほうだ。

……なんで兄ちゃんはあんなことができるのに、アタシはできねえのかって。なんで兄ちゃんはあんな強い決意ができてたってのに、アタシは逃げ出しちまったのかって。

なんで兄ちゃんは死ぬことすらも、死んでもこの身を焦がすことを受け入れることができたのに、アタシはそんな兄ちゃんの姿が受けられねえんだよって。

……
どうして姉さんは灰燼から立ち上がることができたのに、私はただ陰に隠れて泣くことしかできないのだろうか?
お前はどうしたいんだ、ラフシニー?

……「君のために、私は生涯知る限りの愛と夢を書き連ねた」……

「けど火に燃えるような狂乱と歓喜の渦中に、愛と夢を許容してくれるような場所はない」……

は?

おいお前……まさかこんな空気の中でポエムを読んでるわけじゃねえだろうな?

えっ、ウソ、マジで?アタシにポエムを?なんなんだよお前、自分には教養があるって見せびらかしたいのかよ?

ごめんなさい……私、なんて伝えればいいか。

人を励ましたり、慰める言葉なら、たくさん出て来るけど……それは全部、私から出たものじゃない。

あっそ……ならもう勘弁してくれ……

……
顔を両手で覆い隠したセルモン。
彼女の悲しみもまた、ここで押し黙ってしまったダブリン兵と同じように、深緑色をした格好に包まれていった。
そして「夢を見た……」と、彼らは囁きながらこう続けた。

何年も前、アタシらがまだヴィクトリアの荘園で働いてた時の話なんだが。

ある日兄ちゃんが、仕事とか全部ほっぽり出して遊びに行こうぜって言ってきたんだ。

……そっからすげー歩いたよ、農地区画の外縁部まで行ってな。下に広がってる荒野を見たんだ。

どこまで続く広い土地、どこまでも野花が咲き誇っていたよ。んで兄ちゃんが、あれがターラーだって言い出したんだ。

ほんでバカで大袈裟な与太話を話しながら、風が吹く中、大声で歌でも歌ってたっけなぁ。

ヴィクトリア人は俺たちの言葉を奪って、俺たちは上手く言葉で言い表すことができなくなったから、愛とか悲しみとかの感情を古い民謡に残すしかできなくなっちまったって言ってたよ。

それに、今俺たちがこうして仕事をほっぽり出したのも、ある意味ヴィクトリア人に対する反抗の一つだから、俺たちは偉いことをしたんだって言ってたっけ。

あの頃の兄ちゃんは本当に自信に満ち溢れていたよ、マジで物語に登場する英雄になろうとしていたなぁ……ふっ。

それはアタシも一緒だったっけ。

……お前が兄ちゃんに残してくれたあの火、キレイだったよ。あの時アタシらが見た一面の野花を思い出すぜ。

でも、本物の花というわけではないよ。それに……
「生から死までの、瞬く刹那みたいな人生を。」

……掴み取ることすらできない。

いいんだ、気にしてねえよ。

兄ちゃんがいつか死ぬのはアタシにも分かっていたさ。ダブリンを探し始めた時だって、アタシも死ぬ覚悟はしていたもんだからな。気にしちゃ……いねえよ。

兄ちゃんのことも、ホラを吹いて夢を見ていた時みてぇに、英雄になれるとも思っちゃいなかったしな。

そこでなんだが、リード……本心を聞かせてくれねえか、お前の本心を。

兄ちゃんが死んでも追い求めていたもの……ダブリンが約束してくれた未来は、ありゃただの偽物だったのかよ?

……
暗い暗い夜の中、明るい炎が槍先から現れた。
炎の明かりに照らされてリードが目にしたのは、ようやく頬を伝ったセルモンの涙であった。